お茶の用語辞典(り)
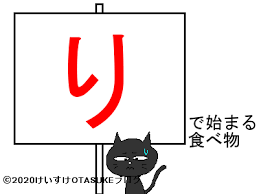
利休百会期(りきゅうひゃくえき)
最も有名な会記のひとつ。利休が最晩年に出席したお茶会の記録。一番最後の記録は1591年の1月に徳川家康を招いています。
利休七哲(りきゅうしちてつ)
利休の死後、活躍する高弟たちを分かりやすくまとめたものです。利休のひ孫、後の表千家の実質初代(公式には初代は利休ですので、四代目)お家元の江岑宗左(こうしんそうさ)が「利休弟子衆七人衆」として次の七人をあげました。
昔から日本人はランク付けが好きなのか、ランキングされています。お茶のことはよく知らなくても、漫画の主人公にもなって一般になじみの深い古田織部はもちろん七哲にランクインしています。将軍になった徳川秀忠の茶の湯師範にまでなった古田織部(ふるたおりべ)ですが、宗左は彼のことをボロクソに評価しています。ですので最下位の七位は古田織部。六位が牧村兵部(まきむらひょうぶ)、五位は瀬田掃部(せたかもん)、四位は芝山監物(しばやまけんもつ)です。この監物は利休と懇意であったとされています。
ではベスト3の発表です。ここからは織部同様、歴史の教科書に出てくるメンバーなので名前を聞いたことはあると思います。三位は細川三斎(ほそかわさんさい)。二位は高山右近(たかやまうこん)、そして一位が蒲生氏郷(がもううじさと)でした。
ただ、その後の茶書によってはメンバーが若干変わっていることを書き添えておきます。例えば、前田利長が入っていたり、織田有楽や千道安が入っていたりとばらばらです。しかしどの茶書にも登場するのが、蒲生氏郷、細川三斎、古田織部、の三人です。
臨済録(りんざいろく)
茶室の床に荘られる掛け物の中心が『一行物』と呼ばれる禅語です。その出典元の多くが「語録」と呼ばれる禅宗の偉いお坊さんの言行録です。そのうちの一つがこの臨済録で、正式名称は『鎮州臨済慧照禅語録(ちんしゅうりんざいえしょうぜんじ)』です。この方は臨済宗の宗祖で唐代の人(もちろん中国人)です。死後に弟子たちがまとめたものが原型になっているそうです。弟子に対しては厳しく、鋭い指導をされていて「臨済の喝」は有名です。(サンデーモーニングみたいですが…)このサイトの禅語のコーナーでも良く取り上げていますが、有名な禅語を2~3上げておきましょう。
- 無事是貴人
- 且座喫茶
- 随処作主立処皆真
- (意味は『禅語に馴染んでみよう』をご覧ください。)




